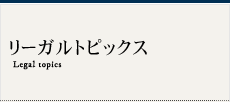ホーム > リーガルトピックス > 平成24年 >社外取締役の選任等に関する会社法改正の動向
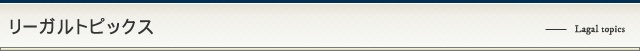
社外取締役の選任等に関する会社法改正の動向
弁護士 礒川剛志
平成24年2月2日更新
| 1.会社法改正の動向 | |
| 株式会社に関する法律は、従前、商法第2編等で規定されていたものが、現行の会社法として平成17年7月26日に公布され、平成18年5月1日に施行された。現在、政府の法制審議会会社法制部会で、会社法制の見直しが議論されており、平成23年12月に中間試案が発表されている。 http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500005.html 中間試案の中には、改正するか否かを含め、両案併記の部分もあり、どこまで法案として採用されるか現時点では確定していない。また、社外取締役の選任の義務付けといった改正には、経済界からの強い反対があるところである。 しかしながら、近時の会社経営陣による一連の企業不祥事により、海外からの日本のコーポレート・ガバナンスに対する不信感を何らかの形で払拭する必要があり、日本株式の市場評価を回復させるためにも改正が実施される可能性が高いと言えよう。 中間試案で取り上げられたテーマは、①企業統治の在り方(第1部)、②親子会社に関する規律(第2部)、③その他(第3部)、の3つに分類されている。第2部の親子会社に関する規律の中にも、親会社の株主が子会社の役員の責任を追及する訴えを認める“多重代表訴訟”の制度等、重要な事項が含まれているが、紙面の都合上、第1部の企業統治の在り方、特に社外取締役の選任の義務付け等、取締役会の監督機能に関する議論にのみ、限定して取り上げたい。 |
|
| 2.取締役会の監督機能の充実 | |
| 取締役会の監督機能の充実という観点から、①社外取締役の選任の義務付け、②監査・監督委員会設置会社制度の採用、③社外取締役及び社外監査役に関する規律、が検討されている。 社外取締役とは、現行法上、「株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。」と定義されている(会社法2条15号)。 これに対して、類似の概念として独立役員がある。東京証券取引所規則に基づく独立役員制度であり、上場会社に対して、独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役をいう。)を1名以上確保することが義務付けられている。 会社からの独立性という意味では、独立役員の定義の方が会社法上の社外性の定義より厳しいということにはなるが、独立役員には社外監査役が含まれている。相当数の上場企業が社外取締役の選任ではなく、既存の社外監査役の存在により、独立役員の上場規則をクリアしているのが現状である。 このような社外取締役あるいは独立役員を選任する趣旨は、主に以下の2つがあると言われている。経営者が自らの経営判断につき監督・評価を行うことは無理があるのであり、外部の目で監督・評価を行うのが合理的である(経営全般の監督機能)。さらに、会社と経営者との間の利益相反を監督する機能も、社内には期待できず、利害関係のない社外取締役による監督が期待される(利益相反の監督機能)。 さらに言えば、会社内部のプロパーの取締役だけで、会社経営に関わる重要事項の判断がなされる場合、会社内部の常識に囚われた判断になってしまい、世間の常識と異なる判断になる可能性がある。これに対して、社外取締役の存在により、多様な意見が経営判断に反映されるという側面があると考える。また、このことは逆に言えば、社内の取締役にとっても、予め社会における経営判断に対する評価を知る機会を持つことになり、後にその経営判断が役員責任を追及されるような内容ではないか否かのチェック機能となるはずである。 |
|
| 3.社外取締役の選任の義務付け | |
| 現状、中間試案において、社外取締役の選任の義務付けにつき、以下の3案が提示されている。 【A案】監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)において、1人以上の社外取締役の選任を義務付けるものとする。 【B案】金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない株式会社において,1人以上の社外取締役の選任を義務付けるものとする。 【C案】現行法の規律を見直さないものとする。 義務付ける社外取締役の人数に関しては、義務付けを規定するA案、B案ともに、1人以上とされており、変わりはない。取締役会の監督機能の充実という意味では、複数の社外取締役の導入が望ましいと思われるが、現実的な経済界からの反発や、社外取締役の人材確保の観点から、1人以上という案に落ち着いたものである。 実際問題としては、取締役の人数自体、会社により異なるのであり、10名以上の社内の取締役がいる中に1名だけ社外取締役が入ることが、監督上どれほどの意味があるのかという気はする。この点、1名だけでも社外取締役がいれば、当該社外取締役が不正を発見し、指摘した場合に孤立したとしても、最終的に辞任という方法で、対外的にアピールする方法があるという意見もある。これについては、辞任という方法を選択することも現実には相当勇気のいる判断であり、孤立した状態の1名の社外取締役にそこまでの役割を期待できるのかという気もする。 もっとも、義務付けという性格上、最低限度の規制としては、1人以上という案も妥当なものであろう。望ましい役員構成としては、上場企業であれば、少なくとも3分の1以上が社外取締役という構成が良いのではないかと考える。 A案とB案の違いは、端的に社外取締役の選任を義務付ける会社の範囲の問題である。A案は、公開会社(上場会社という意味ではなく、株式譲渡制限のない会社をいう。)であり、かつ、大会社であるものを対象とする。すなわち、上場会社でなくても、株主構成の変動可能性が高く、一定の規模を有する会社は、社外取締役の選任を義務付けられることになる。これに対して、B案は、金融商品取引法第24条1項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社を対象とするものであり、典型的には上場会社が対象となる。 社外取締役導入によるコストの負担という点を考えれば、規模的にコストを吸収することが可能であり、かつ一定の社会的責任が期待される上場会社等への義務付けが望ましいと思われる。 |
|
| 4.監査・監督委員会設置会社制度 | |
| 現行会社法上、認められている機関設計の1つとして、少なくとも2名の社外監査役の選任が義務付けられている監査役会設置会社がある(会社法335条3項)。 あるいは、委員会設置会社という機関設計が可能であり、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く会社をいう(会社法2条12号)。この場合、監査役制度はなく、社外取締役を過半数とする各委員会により、経営の監督機能が担われることになる。また、会社の業務執行は、執行役が行うこととされ、アメリカ型の経営と執行の分離を内容とする機関設計を認めるものである。ただ、現状、委員会設置会社制度を採用する会社は少数であり、広く利用されているとは言えない状況にある。 中間試案で導入が検討されている監査・監督委員会設置会社制度は、上記2つの機関設計の中間的なものとして選択肢の1つを加えようとするものである。一見、選択肢を増やすのみであり、それほど問題がないようであるが、実際にかかる制度が導入された場合の影響としては、2通りのシナリオがあるように思われる。 1つ目のシナリオは、多数の企業が社外取締役の選任の義務付けによる負担増を避けるために、監査役会設置会社から監査・監督委員会設置会社へ移行するというシナリオである。この場合、監査・監督委員会設置のため、複数の社外取締役の選任が必要となるが、従前の社外監査役が横滑りする形で、社外取締役候補となることが想定される。結果として、実質的な会社側の負担は少なく、社外取締役の義務付けをクリアできることになるからである。 2つ目のシナリオは、多数の企業が長年親しんできた監査役会制度を廃止せず、社外取締役を単純に1名追加することにより、監査・監督委員会制度を採用しないというシナリオである。不人気な委員会設置会社制度と同じ運命を辿る可能性が否定できないからである。 いずれにせよ、選択肢を増やすという観点では一見良いことのように見えて、結局、複数の制度が併存する形となってしまい、海外の投資家からすれば、益々、日本のコーポレート・ガバナンスの分かり難さが増してしまうのではないかという危惧がある。日本独自のコーポレート・ガバナンスに自信を持つのであれば、監査役会制度で十分なはずであり、一方、そうでないとすれば、監査役会制度を廃止して、全面的に監査・監督委員会制度への意向を義務付けるべきではないか、いずれにせよ中途半端な制度のような気がしてならない。 |
|
| 5.社外取締役の導入の有用性 | |
| 社外取締役の選任の義務付けについては、その有用性という観点で、これによって企業不祥事が完全になくなったり(例えば、監査法人が見抜けないような粉飾決算を社外取締役が発見することは無理であろう)、ましてや企業の業績が短期的に上がるようなものではない。また、経済界からは経営コストを増加させ、事業判断を遅らせるものでしかないとの指摘もある。 しかしながら、社外取締役の多様な意見を経営に反映させることは、まさに多くの日本企業が“閉塞感”を抱える現状に一定の変化をもたらす可能性があるのではないかと考える。例えば、不採算事業であっても、会社の長年の歴史や人間関係に鑑み、社内役員だけでは、閉鎖を決断できないような事情があるかもしれない。近時の一連の企業不祥事が社外取締役の存在によって防ぎ得たか否かは検証が必要であるが、日本企業の特徴として、良くも悪くも、終身雇用制度に裏付けされた会社としての組織性が強すぎるということがある。会社に対する従業員のロイヤリティの高さが日本企業の強みであるとしても、そのような従業員が出世の最終段階として取締役に就任した場合、お世話になった社長や前任者の不正を指摘したり、その意向に反する意見を述べることは難しい。あるいはそのような人間関係がなくとも、社内の常識の中での議論に陥り、結果として閉塞感を生み出してしまうのではないか。 そういう意味で、企業側も社外取締役を政府や証券取引所からの“押し付け”と考えるのではなく、むしろ積極的に複数の社外取締役を選任し、かつ、選任に関しては、できるだけ多様な質の高い人材を確保することを目指すべきである。 この点、もちろん我々のような法律専門家を選任することも選択肢の1つである。日本の弁護士は、基本的に“サラリーマン”経験がないという一点のみを取っても、サラリーマン文化と一線を画する存在であり、貴重な社外取締役候補だと思う。一方、個人的には、必ずしも会社法に精通した法律専門家を選任する意味は実は少ないと考える。会社法上の手続は、顧問弁護士に相談すれば良いのであり、偏った分野の法律専門家よりは、むしろ幅広い法律分野に知見のある経験豊富な弁護士の方が良いかもしれない。 ビジネス経験豊富な人材、女性、外国人、ITに精通した若手といろいろな選択肢がある。逆に、社外取締役を1名と限定した場合には、会社にとって無難な人材を選ばざるを得なくなってしまうのではないかとの危惧があるのであり、1名以上の社外取締役の選任の義務付けを心配するのは、その会社がまさに閉塞感に陥っている証拠のような気がしてならない。 |
|
| 以上 |