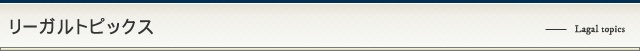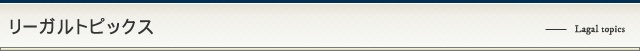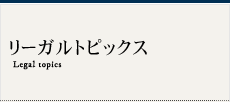ホーム > リーガルトピックス >令和7年>投資詐欺の口座名義人の責任
投資詐欺の口座名義人の責任
弁護士 寺中良樹
令和7年1月6日更新
昨年、大阪地方検察庁のもと検事正(大阪地方検察庁のトップ)が在職中に部下である女性検事に対して性的暴行を働いたとの容疑で逮捕起訴されたとの事案が発生しました。もと検事正は第1回の公判期日では公訴事実を認めましたが、その後記者会見し、無罪を主張する方針に転ずるとのことです。
公訴事実を認める(いわゆる自白)公判の途中から否認に転じるということは法律上は可能なことです。有名なものとしては、「松橋事件」と言われている再審無罪となった事件もそうでした。もと検事正の新たな主張が真実であるのか否か、部外者なので立ち入ったコメントは差し控えたいと思いますが、仮に「同意が得られていると思った」という理由で無罪となったとしても、もと検事正のその後の人生にとってその無罪が良い方向に働くのかどうか、考えてしまいます。
さて近時、特殊詐欺の中でいわゆる投資詐欺と言われるものが多発しています。これにはかなり決まった特徴があり、
|
| ・ |
SNS(多くはLINE)上で「投資アドバイザー」と称する者が多数長文の投資情報のようなものを一方的に投稿し(それをもてはやすサクラも多数登場します)、
|
| ・ |
それに興味を持った被害者が指定先にアクセスすると、正体不明の「取引所」での取引を勧誘され、 |
| ・ |
それを承諾すると「取引所の資金管理者」に連絡するよう指示され、「資金管理者」から「取引資金」の送金先の銀行口座を指定される、 |
という順番です。
何回も送金する場合、その都度別の口座を指定されるのが通常です。
これらの送金先の口座は加害者自身のものではなく、他人から取得した口座で、これらの者に口座を使われた者がいるわけです。
しかし、自分が何もしていないのに、自分の口座をいつの間にか詐欺師に使われるということはほとんど見かけません。大概は、誰か(多くは素性の知れない者)に勧誘されて口座を作り、通帳・キャッシュカードや口座情報(ID・PW)を提供したため、これを犯罪行為に使われてしまうということのようです。
また、被害者が送金先口座として指定された口座には、思いの外、法人名義口座が多いと感じます。法人名義口座は個人名義口座よりも信用があるように見え騙しやすいので、詐欺グループは法人口座を優先的に集めようとしているのではと推測します。法人口座の提供の経緯として、役所から補助金を受けるためとか投資家から資金の融通を受けるためと言われて通帳キャッシュカードを貸すというパターンがあるようです。
いずれの場合も、自分が詐欺グループに加担しているという(はっきりした)認識なくして安易にしてしまっているのですが、犯罪行為そのものに関与していないからと言って、何の責任もないということにはなりません。
まず、犯罪収益移転防止法(28条2項)は、正当な理由がないのに、有償で、通帳やキャッシュカード等の譲渡をする行為に罰則を科しています。いわゆる闇バイトのような形で口座を提供した者についてはこの法律の適用があります。
また、有償でなかったとしても、責任がないことにはなりません。提供した口座が実際に詐欺に使用された場合、被害者から民事上の不法行為責任を追及される可能性があります。自分が詐欺行為に加担するつもりがなかった場合でも、「過失による幇助行為」という理屈で損害賠償責任を認める裁判例が複数あります。たとえば東京地裁平成28年3月23日判決(平成26年(ワ)第6822号)、東京地裁平成29年5月10日判決(平成29年(ワ)第34283号)、東京地裁令和5年11月13日判決(令和5年(ワ)第4684号)などがあります。
被害者からすると、実際の加害者の身元を暴きその責任を追及することはかなり困難なので、口座名義人の身元を調査しその者に民事上の責任を追及するというのが被害回復の第一手段となります。投資詐欺被害の被害金は、100万円1000万円というかなり大きな単位になりやすいことが特徴で、安易に他人に口座提供することは、思わぬ莫大な責任を負うことにもなりかねません。安易な判断をしないことが第一ですが、万が一自分が他人に口座情報を提供してしまったことに気づいた場合は、直ちに銀行口座を停止し悪用を防ぐことが必須です。
|
|
| 以上 |
|
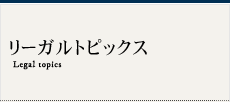
-