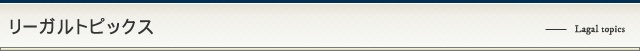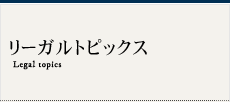ホーム > リーガルトピックス >令和元年 >負担付遺贈について
負担付遺贈について
弁護士 松本史郎
令和元年7月16日日更新
| 1 設例 |
Aは、平成元年、遺言書を作成し、その中で「甲土地をBに遺贈するが、Bは共同相続人C、D、Eに各2000万円ずつ支払え」と記した(B、C、D、EともAの子供)。
Aは、上記遺言を遺して平成31年4月に死亡した。遺産は甲土地だけである。
甲土地の価格は、平成31年の時点で2000万円程度である。
|
| 2 負担付遺贈(民法1002条)について |
| (1) |
負担の額(設例では6000万円)が遺贈される対象の価額(設例では甲土地の時価2000万円)を上回るときは、受遺者(B)には、その対象の価格(2000万円)を上限として負担の履行義務が生じる。
|
| (2) |
受遺者(B)が負担を履行しない場合、相続人(CないしE)は、相当の期間と定めて催告をし、その期間と徒過したときは、遺贈の取消を家庭裁判所に請求することができる。ここでの取消は、いったん生じた遺贈の効力を負担の不履行を理由として事後的に失効させるものであり、契約不履行による契約解除に近い法律行為である。
|
|
| 3 Bが負担付遺贈を承認するか、放棄するかを判断する際に知っておくべき事項 |
| (1) |
負担が遺贈の利益よりも大きいときは、遺贈全部が無効となるのではなく、遺贈の価格を超過する負担の部分だけが無効となる。
つまり、設例で6000万円の負担中、4000万円の負担部分が無効となる。
|
| (2) |
時価2000万円の甲土地の遺贈を受けるために、2000万円の負担を履行するのであれば、負担付遺贈を放棄して、BないしEの4人で各4分の1の持分で甲土地を共同相続するとすれば、Bの負担はなく、その後、CないしEに各500万円を支払って持分を買い取ることができれば1500万円(500万円×3人)を負担するだけでBは甲土地全部取得することができる。
しかし、Bがもし遺贈を放棄すると、負担の利益を受けるべきCないしEが自ら受遺者となることができる(1002条2項)ため、Bが甲土地を取得する機会を失うこともありうる。
したがって、Bがどうしても甲土地全部を取得したいのであれば、Bは遺贈の目的物(甲土地)の価格と負担の額が同一であっても(すなわち2000万円の負担を負うことになったとしても)、遺贈を放棄することは得策でないといえる。
|
| (3) |
遺贈の目的物の価格と負担の価格との大小を決める時点について、考え方は、遺言が効力を生じた時か、受遺者が遺贈を承認したときか、負担を履行するときかに分かれるが、通説は、負担を履行するときを基準として定めるとされている。
|
| (4) |
負担の履行の限度について、当事者間に争いがあるときの法的アクションについて、設例で、BはC、D、Eに各666万円(合計2000万円)を支払うことを申し入れたが、CないしEは、甲土地は少なくとも4500万円は下らないと主張して、BとCないしEとの間に負担限度の争いが生じた場合の対処方法として、次のアないしエが考えられる。
| ア |
C、D、Eから負担の履行を求める訴訟が起こされるまで待って、その訴訟で問題の解決を図る(地方裁判所)。 |
| イ |
C、D、Eが負担付遺贈の取消を求める審判を申立てるまで待って、その審判の中で問題の解決を図る。 |
| ウ |
BがC、D、Eを相手に666万円を超える債務(負担)がないことの債務不存在確認請求訴訟を提起して、その訴訟の中で問題の解決を図る(地方裁判所)。 |
| エ |
Bがウと同趣旨の申立の一般民事調停又は一般家事調停を申立て、その調停の中で問題の解決を図る(簡易裁判所又は家庭裁判所)。
|
ア、イの場合は、C、D、Eのアクション待ちなのでBの地位が当面不安定になる。早期に不安定な地位を脱出したければ、ウ又はエの方法でBの方から法的アクションを起こすことも考慮すべきである。
|
|
| 以上 |
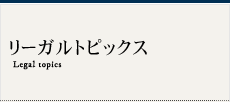
-