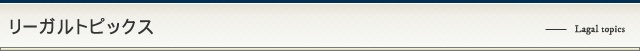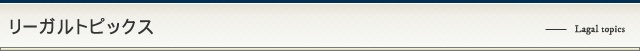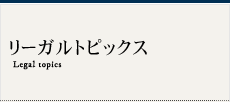ホーム > リーガルトピックス >平成29年 >ベンジャー企業の法務
ベンチャー企業の法務
弁護士 礒川剛志
平成29年10月5日更新
| 1.はじめに |
当事務所では、スタートアップ段階の企業、上場準備段階を迎えている企業、あるいは見事、上場を果たした企業など、多くのいわゆるベンチャー企業と顧問契約を締結させていただいています。これらの企業から日々、法律相談を受ける中で、他の中小企業の顧問先とは異なったベンチャー企業特有の法律問題があることから、これらにつき解説したいと考えました。
|
| 2.ビジネスモデルに特有の法律問題 |
| 1) |
ベンチャー企業は、典型的にはITを使用して、これまで世の中になかったビジネスモデルを提供する場合があり、そのビジネスモデルが既存の法規制や許認可を満たしているのかという問題があります。
例えば、病院向けに有料で患者紹介を行うウェブサイトを運営するというビジネスを思いついたとします。一見、このようなビジネスは適切な病院を探す患者にもメリットがあり、経済的な安定を求める病院にもメリットがあることから、良いビジネスモデルのようにも思われます。しかしながら、このような患者紹介は、「経済上の利益の提供による誘引」に該当することから禁止されており(療養担当規則)、コンプライアンスに反するビジネスモデルということになります。
|
| 2) |
また、ウェブサイトでのサービスを展開する場合、直接、顧客と契約書を締結せず、ネット上での処理となることから、適切な利用規約を準備する必要があり、B
to Cのビジネスである場合は、特定商取引法、消費者契約法、個人情報保護法など消費者や個人を守る法規制を遵守した内容にする必要があります。
|
|
| 3.企業の未成熟性から生じる法律問題 |
| 1) |
ベンチャー企業は、若い代表者、若い役員、若い従業員が構成員となっており、よく言えば、柔軟で勢いのあるメンバーによって運営されていますが、その一方で、組織自体や個々のメンバーの社会経験が未成熟な場合がありえます。
ある程度、成熟した企業であれば、経験を積んだ人事担当者、法務担当者がいるわけですが、スタートアップの段階では、1人の管理担当役員が経理、人事、法務を兼務しているといったことも珍しくありません。例えば、インターネットで見つけた契約書の雛型をそのまま使用して取引先と契約を締結したり、顧問税理士さんに契約書を見てもらって法律的なチェックまでしてもらったと誤解しているケースがあります。
|
| 2) |
事務所の賃貸借契約書、従業員との雇用契約書、仕入元や販売先との取引基本契約書など、スタートアップの段階でも、企業は多くの契約を締結することになります。これらは、通常の取引を継続している場合は特に問題になることはありませんが、いったんトラブルが発生した場合には、契約書に従った判断がなされるため、企業にとって大きなリスクとなる可能性があります。
例えば、あるベンチャー企業が順調に成長してきたため、事務所を移転したいと考え、条件の良い場所を格安の賃貸条件で見つけることができた。ところが、いざ従前の事務所の賃貸借契約を中途解約したいと考えたところ、その賃貸借契約書に中途解約条項がなかった。賃貸人が合意解約に応じてくれれば良いですが、場合によっては、賃貸借期間の満了まで移転を延期しなければなりません。通常の賃貸借契約書には、借主からの中途解約条項が規定されていますが、解約予告期間が6か月と長期になっている場合も同じく6か月待つか、6か月分の賃料相当金を支払うかという問題が生じます。
|
| 3) |
その他、近時では労務問題が社会問題化しています。ベンチャー企業の従業員が目標達成のため長時間労働で昼夜を問わず、頑張るというのはありそうな話ですが、当然、過重労働の問題や残業代の問題が発生します。特に上場審査に際して、残業代の問題が発覚すると、過去2年間の残業代が潜在的な債務として上場の妨げになる可能性があり注意が必要です。
|
|
| 4.資金調達に関連する法律問題 |
| 1) |
アイデアはあるが、資金がないというのがベンチャー企業であり、このような場合、アイデアを実行するための資金を用意すべく、ベンチャーキャピタルやファンド、あるいは既存の大企業から出資を受けることになります。このような出資を受ける場合には、出資後の資本構成や、株式の評価、役員派遣の有無、議決権の有無及びIPOまでの期限等の出資条件が問題となります。特に出資後の資本構成や議決権の有無は十分に検討しなければ、将来的に創業者による経営の足枷になる可能性もあります。
|
| 2) |
株式投資契約書、株主間契約書といった契約を締結するとともに、会社法に従った手続きとして役員会、株主総会の開催が必要となります。
|
|
| 5.M&Aに関連する法律問題 |
| 1) |
ベンチャー企業は、IPOを目指す過程で、事業規模の拡大を求め、自らが買主としてM&Aに関与するケースも多く、その一方で、IPOとは違うエグジットとして、自らの事業を他の企業に売る、売主となるケースもありえます。
|
| 2) |
買主としてM&Aを行う場合には、安易に売上の拡大を求めてM&Aをしないことが重要であり、最初の段階で、如何なる目的でその事業を買うのかを明確にする必要があります。例えば、既存の事業とのシナジーが具体的に見込めるとか、対象企業の技術を取得したいといったシンプルで具体的な目的が必要です。M&Aの手続は一般的に、守秘義務契約を締結し、基本的な資料の開示を受け、基本合意書を締結した後、デューデリジェンスを実施する。デューデリジェンスを行って特段問題なければ、正式契約(株式譲渡契約あるいは事業譲渡契約)を締結するという流れです。
しかしながら、デューデリジェンスをした上での最終判断と言いつつ、仲介アドバイザーはできるだけ取引を成立させようとしますし、会社担当者もいったん始まったディールを途中で中止するというのはなかなか勇気のいる判断になります。最初に打診を受けた時点で、本当に価値のあるM&Aなのかを判断する必要があるわけです。
|
| 3) |
また、M&Aを実施する場合は、対象企業に簿外債務がないか、潜在的なリスクがないかをデューデリジェンスでチェックする必要があります。例えば、対象企業に既に述べたような残業代の問題があるとすれば、それは潜在的なリスクということになりますし、買収を中止する、あるいはそのリスクを織り込んだ安い取得価格にするといった判断が必要になります。
|
| 4) |
さらに、対象企業を株式譲渡で取得するのか、事業譲渡で取得するのかといったM&Aの手法に関する判断も必要です。端的に言えば、株式譲渡の場合は対象企業を丸々取得することになるので、手続が簡便という一方、良い部分も悪い部分も(簿外債務も含め)全て取得してしまうというデメリットがあります。事業譲渡の場合は、良い部分だけを選んで取得できるというメリットはあるものの、許認可の手続が再度必要になったり、契約先との契約を蒔き直す必要があるといったデメリットがあります。
|
|
| 6.IPO等に関連する法律問題 |
IPOに際しては、企業のガバナンスやコンプライアンスが審査されることになり、役員会が適切に開催されてきたかや、前述の残業代の問題などの潜在的なリスクがないかがチェックされることになります。既に述べたような種々の法律問題に関して場面場面で適切な対応をされていれば、IPO段階で特に法務リスクが課題となることはないということになりますが、逆に言えば、IPO段階で法務リスクが顕在化した場合、過去に遡って修復するのが困難なケースもあることから、法務リスクがIPOの障害となってしまう場合がありえます。
また、IPOではなく、他の企業による買収という形のエグジットもありえますが、同じく法務リスクが顕在化した場合には、買収が中止されたり、買取価格を安く叩かれる原因となってしまうわけです。
|
| 7.まとめ |
| 日本経済が継続的に発展するためには、多くのベンチャー企業が誕生し、多くのイノベーションを成し遂げることが必要と考えます。その一方で、ビジネスにはスポーツと同じく種々のルールがあり、勢い余ってルールを破らないよう、ベンチャー企業経営者の皆さんが法務に関心を持っていただけると幸いです。 |
|
| 以上 |
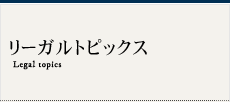
-