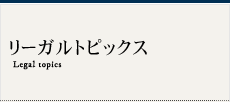ホーム > リーガルトピックス >平成26年 >血縁上の父子関係がないことを知りながら認知した者が認知の無効を主張することの可否
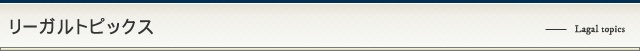
血縁上の父子関係がないことを知りながら認知した者が認知の無効を主張することの可否
弁護士 小西宏
平成26年2月4日更新
| 1 はじめに | |||||
| 先日、血縁上の父子関係がないことを知りながら認知した者が認知の無効を主張することの可否に関する最高裁判決(平成26年1月14日)が出されました。実務上参考となる判例だと思われますので、ご紹介させていただきます。 |
|||||
| 2 事案(※一部簡略化しています) | |||||
| Aは、平成15年3月に、Cの母であるBと婚姻し、平成16年12月、C(平成8年生まれ)の認知(以下、「本件認知」という)をしました。AとCには血縁上の父子関係はなく、Aは、本件認知をした際、そのことを知っていました。 AとCは平成17年10月から共に生活するようになりましたが、一貫して不仲であり、平成19年6月頃、Aが遠方で稼動するようになったため、以後、別々に生活するようになりました。AとCは、その後、ほとんど会っていません。 その後、AとCの間に血縁上の父子関係がないことを知りながら認知したAが、Cに対し、認知の無効の訴えを提起しました(なお、Aは、Bに対し、同訴えと同時に、離婚を求める訴えを提起し、Aの離婚請求を認容する判決がなされています。)。 |
|||||
| 3 判決要旨 | |||||
| 以上の事実関係において、最高裁は次のとおり判示しました。 「血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知は無効というべきであるところ、認知者が認知をするに至る事情は様々であり、自らの意思で認知したことを重視して認知者自身による無効の主張を一切許さないと解することは相当でない。また、血縁上の父子関係がないにもかかわらずされた認知については、利害関係人による無効の主張が認められる以上(民法786条)、認知を受けた子の保護の観点からみても、あえて認知者自身による無効の主張を一律に制限すべき理由に乏しく、具体的な事案に応じてその必要がある場合には、権利濫用の法理などによりこの主張を制限することも可能である。そして、認知者が、当該認知の効力について強い利害関係を有することは明らかであるし、認知者による血縁上の父子関係がないことを理由とする認知の無効の主張が民法785条によって制限されると解することもできない。 そうすると、認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができるというべきである。この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない。」 |
|||||
| 4 解説 | |||||
| (1) 判決の概要 | |||||
| 民法786条は、「子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。」と規定し、子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実、すなわち、認知はしたものの血縁上は父子関係にないことを主張することにより、いつでも認知の無効を主張することができるとしています。 この最高裁判例のポイントは、父子関係にないことを知りながら認知をした者(以下、「認知者」といいます。)が同条の「利害関係人」にあたり、その認知無効の訴えも認められるとしたことです(なお、1人の反対意見があります。)。 |
|||||
| (2) 多数意見の理由 | |||||
| C側は、気まぐれな認知と身勝手な無効を許すことになり、その結果、認知により形成された法律関係を著しく不安定にし、子の福祉を害することになるなどの理由により、認知者の認知無効の主張は許されないと反論としていました。 しかし、多数意見は、①認知者が認知をするにいたる事情が様々であることから、常に気まぐれな認知になるわけではなく、認知者自身による無効の主張を一切制限することは相当でないこと、②血縁上の父子関係がない場合には利害関係人によってそれを理由に認知無効が主張されるから、認知者の無効の主張を制限しても、法律関係の安定性確保・子の福祉の確保の実効性はわずかなものでしかなく、あえて認知者自身による無効の主張を制限する理由はないこと、③具体的事案に応じて無効の主張を制限したければ権利濫用の法理などによることが可能であることを挙げて、C側の反論を退けました。 |
|||||
| (3) 権利濫用の法理 | |||||
| では、認知者による認知無効の主張は全く制限されないのでしょうか。この点について、最高裁は、前記のとおり権利濫用の法理などにより制限することも可能であると判示しています。今後は、認知者の認知無効の主張は原則として可能となり、個別具体的な事案に応じて、権利濫用の法理により主張が制限されることになると思われます。 ただ、この権利濫用の法理がいかなる場合に適用されるのかは、今後の事案の集積を待つほかありません。 参考になるものとして、この最高裁判決の原審(平成23年4月7日広島高裁)において権利濫用の法理の判断がなされています。その認定された事実関係を見ますと、Bはフィリピン人で、Cはその連れ子であったという事情があり、認知無効の訴えが認められると、認知は遡ってなかったことになり、Cの日本国籍の取得も無効となって在留資格を喪失し、フィリピンに強制退去させられるという事情がありました。他方で、AとCは一貫して不仲であり、今後も修復の可能性はほとんど考えられないこと、C(当時14歳)は、8歳までフィリピンで実兄らと生活しており、フィリピンには実兄も、祖母もいるほか、Bとは母語であるタガログ語で会話する生活を送っていること、加えて、Aは、現在、福祉に頼って生活しているという事情も認められています。 原審は、以上の事情を考慮すると、C(既に血縁上の父とは死別している)が、法律上の父を失うことになるとしても、精神的・経済的に不利益が大きいということはできないとしました。 また、本件は、AとBとの婚姻に伴ってされた連れ子養子の実質を有するものであるところ、AとBの婚姻関係が破綻した場合であっても、これを解消する制度がないという事情もあり、Aの認知無効の主張は権利濫用にはならないとしました。 今回の事案はかなり特殊ですので、原審の判断を一般化することは困難ですが、権利濫用を判断するにあたっては、子の精神的・経済的な不利益があるのか否か、認知無効の主張を行うに至った事情などが重要になるという点で今後の参考になるかと思われます。 |
|||||
| 以上 | |||||