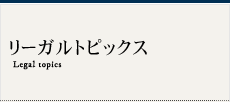ホーム > リーガルトピックス >平成25年 >債務整理の方針についての説明義務違反
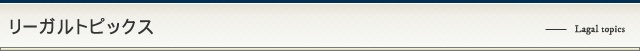
債務整理の方針についての説明義務違反
弁護士 天野雄介
平成25年11月6日更新
| 1 | 依頼者から消費者金融からの借り入れなどについての債務整理の依頼を受任した場合、受任時点で債務整理の大まかな方針を立て、債権者からの回答が出揃った段階で、方針を確定させることが多いです。 もっとも、方針が確定しても、債権者との交渉において方針変更を余儀なくされることも多く、大きく方針変更(任意整理から自己破産へなど)をすることも少なくありません。 |
||||
| 2 | そのような場合の受任弁護士から依頼者への説明義務違反が認められるものとして、平成25年4月16日、最高裁判決が出されました。 事案は、「依頼事項は5社の任意整理であり、利息制限法に基づき引き直し計算を行ったところ、3社に過払金が発生し、2社(A社、B社)に残債務が残った。過払金を3社から回収し(約160万円)、2社の残債務がそれぞれA社約38万円、B社約12万円(ただし、一連計算とするか個別計算とするかで争いがあり、債権者の主張は約30万円)であったため、残債務がある2社にそれぞれ残債務の8割である、A社30万9000円、B社9万4000円の提示をし、A社とは和解が成立したが、B社とは合意に至らなかったため、残金約50万円を依頼者に返還し、B社の債務については消滅時効を待つこととした」というものです。 最高裁は、消滅時効を待つという方法は大手消費者金融会社相手であれば非現実的であり、にもかかわらず時効を待つという選択肢についてのリスク(遅延損害金の加算や債務整理が長期間終了しないなど)について依頼者に十分な説明をしていないとして、受任弁護士の説明義務違反を認定し、依頼者の損害を算定するため、高等裁判所に事件を差し戻しました。 |
||||
| 3 | 相手が大手消費者金融会社であれば、時効を待つという選択肢はあまり現実的ではなく、そのリスクについての説明が不十分であったことから、最高裁の結論自体は妥当であると考えられます。 もっとも、このような事案の場合、依頼者に十分な説明を行った上で、どのような処理を行うかというのは非常に悩ましい問題です。 まず、最初の問題は、債権額に争い(12万円と30万円の違い)がある点です。 受任弁護士としては、自己の主張額が正当である根拠を示すとともに、出来るだけ自己の主張額に近い金額での和解を目指すことになろうかと思いますが、それでも金額に開きが生じる場合も少なくありません。 また、債権者が元本額及び遅延損害金全額を主張し、一切の譲歩をしない場合もそれを受け入れるかという問題もあります。 弁護士における任意整理の際には、債権者間の公平を図る必要があり、一切の譲歩をしない債権者に言われたとおりの金額を支払うことは、依頼者の経済的更生に理解を示し早期の和解に応じた債権者より、一切の譲歩をしない債権者を優遇すること、すなわち「ごね得」を許すことになることになるためです。 そのため、どうしても合意に至らない場合は、①債権者の提示額どおり支払う、②特定調停や債務不存在確認(12万円を超えて債務は存在しない)など法的手続きを取る、③債権者が妥協するまで待つなどの方策を、依頼者と協議して決めるということになります。 ③について、消滅時効を待つという方法はあまり採りませんが、時間を掛けて、債権者の方針の変化や状況の変化を待つということはよくあります。 どのような方針とするかは①債権者の属性(債権者が大手か中小かによって訴訟リスク・強制執行リスクが異なります)、②債権者の訴訟・和解方針、③依頼者の属性(サラリーマンか年金生活者かによって強制執行リスクが異なります)などによって判断すべき問題ではありますが、最終的には依頼者の意思によるということになります。 このような場合、私の経験では、「先生が決めてください」や「先生ならどうしますか」などと言われ、受任弁護士が判断して決めることが多いのですが、だからといってリスクの説明もせず受任弁護士の独断で処理していくことは、依頼者の意思と乖離する可能性もあるのであって、最高裁の示すとおり、弁護士としては説明義務を果たしていないと考えられます。 現在の弁護士には適切な事件処理と同時に適切な説明責任が課せられているという点を再認識させられる判例です。 |
||||