
�z�[�� > ���[�K���g�s�b�N�X >����25�N >�p���_�̎���-2
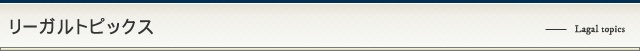
�p���_�̎����|2
�ٌ�m�@�E�썄�u
����25�N5��15���X�V
| �@�@�`�@�p���_�̎����|1�@�Â��@�` |
|||||
| �R�D�p���_�̓��� | |||||
| �@�p���_�̓����͂Ƃɂ������e���ڍׂŒ����ł��邱�Ƃ��w�E�ł��܂��B�P�ɑ���̌��ϕ��@�╨�i�̈��n�������L�ڂ��邾���ł͂Ȃ��A�����I�ɔ�������\���̂��郊�X�N������ԗ�����悤���[������߂��Ă��邩��ł��B �@�܂��A����p��ƈقȂ錾����A�Ɠ��̗p�ꂪ�g�p����Ă���̂������I�ł��B�Ⴆ�A�uA�́Z�Z�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�A�uA�́Z�Z������̂Ƃ���B�v�Ƃ����Ӗ��ŁA�uA shall �c�v�Ƃ����\�����g�p����܂����A����p��̂悤��will���g�p���邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���B�܂��A�uA�́Z�Z���邱�Ƃ��ł���B�v�Ƃ����Ӗ��ŁA�uA may �c�v�Ƃ����\�����g�p���܂����Acan���g�p���邱�Ƃ͂���܂���B����ɁA���{��̌_�Łu���i�i�d�q���i���܂ށB�j�v�Ƃ������K��̎d�������܂����A�p���_�̏ꍇ�A�uProducts, including but not limited to electronic parts�v�Ƃ킴�킴�u���i�i�d�q���i���܂ނ��A����Ɍ��肷���|�ł͂Ȃ��j�v�Ƃ������ܑ̂Ԃ��������������܂��B �@�p���_�������������ꂽ�ꍇ�ɖ|���Ђɖ|����˗������P�[�X�������Ǝv���܂����A�������Ɠ��̌����ł��邪�̂ɁA�|���Ђ��@�������̖|��Ɋ���Ă��Ȃ��ƁA�Ӗ��s���̓��{��o���オ���Ă��܂��Ƃ������Ƃ����肦�܂��B |
|||||
| �S�D�p���_�̍\�� | |||||
| �P�j�@�O�� | |||||
| �@�����҂���肷�����_��Ɏ������o�܁A�_����������L�ڂ���܂��B | |||||
| �Q�j�@�{�� | |||||
| �@�@��`���� | |||||
| �@�K�����݂���Ƃ����킯�ł͂���܂��A�����̌_�̏ꍇ�A�`���ɂ�������̒�`�������������̂�����܂��B | |||||
| �A�@������� | |||||
| �@�̔��_��ł���A����̌��Ϗ����╨�i�̈��n�������L�ڂ��邱�ƂɂȂ�܂��B���ɔ���̌��͂������P�[�X�ł́A����Ɉ��ʂ̍ɂ���Ɋm�ۂ��邱�Ƃ��_���`���t�����Ă������������܂��B���̂悤�ȏꍇ�A���傩�炷����̂悤�ȋ`�������ۂɗ��s�ł��邩�A���s�ł��Ȃ������ꍇ�̃y�i���e�B���ǂ��Ȃ��Ă��邩�A��������~���ꂽ�ꍇ�̍ɂ̔��������Ă��炦��̂��A�Ƃ������ϓ_����̃`�F�b�N���K�v�ƂȂ�܂��B �@�܂��A�̔��_��ő��̔���ɂ��������i�Ŕ̔����Ă���ꍇ�ɂ́A����͓��Y����ɑ��Ă����̉��i�܂Ŕ̔��P���������Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ���������ɗL���ȏ����������Ă���P�[�X������܂��B |
|||||
| �B�@�_����� | |||||
| �@�قƂ�ǂ̌_��Ō_����Ԃ���߂��Ă���A�Ⴆ�Ζ{�_�������R�N�ԁA�_����ԏI���O�Q�����ȓ��Ɉًc���Ȃ���Ύ����X�V����Ƃ����������ɂȂ��Ă��܂��B�_����Ԃ̒��Z�A���r�������Ƃ����������͓��ɏd�v�ł��B�Ƃ����̂��A���Ɏ���J�n��A���ۂ̎v�f����O�ꂽ���߂Ɏ���𒆎~�������Ƃ����悤�ȃP�[�X�ł��A�_����Ԃ��Z����Ό_����ԏI�����_�ōX�V�����Ȃ��A���邢�͒��r������������Ό_����Ԃ̓r���ł����r��\�ł��B���ɑ����������ꂽ�_�̃h���t�g�̏ꍇ�A��������炵�����r���ł��Ȃ��悤�ȏ����ɂȂ��Ă���P�[�X������̂Œ��ӂ��K�v�ł��B | |||||
| �C�@��ʏ��� | |||||
| �@��ʏ����Ƃ��ẮA�i���ۏ؏����A�댯���S�����A���Q���������A�������������Ȃǂ̏����������Ă���A�����͌_�Ɉ�ʓI�Ɍ���������Ƃ��āA�{�C���[�v���[�g�iBoiler
plate�j�����ƌĂ�܂��B����������Ȏ��ɂ͖��ƂȂ�܂��A�����g���u���������������ɂ͏d�v�ƂȂ�����ł���A���Ղɓǂݔ���Ƒ傢�Ɍ�����邱�ƂɂȂ�܂��B �@���ɔ̔��_�ł́A����͌������i���ۏiWarranty�j��v�����܂����A����͂ł��邾���ƐӁiIndemnity�ALimited Liability�j���ꂽ���ƍl���A�����s���l�܂��Ă��܂��P�[�X������܂��B���ǂ͂ǂ��炪��������Ō����s���Ă��邩�Ō��܂��Ă��܂��킯�ł����A�{���͉��i�����Ƃ̌������Ō�������Ƃ������l�����������I�Ȃ͂��ł��B�Ⴆ�A�i���ۏ�t���Ȃ�����Ɉ��̒l����������Ƃ������������肤��킯�ł��B |
|||||
| �R�j�@�ʎ� | |||||
| �@Appendix�Ƃ����`�Ő��i�̎d�l����v���C�X���X�g�����Y�t����邱�Ƃ�����܂����A�@�I�ȓ��e���܂܂��P�[�X������A�@���S���҂͕ʎ������ɂ��Ă��ǂݔ���Ȃ��悤���ӂ��K�v�ł��B |
|||||
| �T�D�����@�ƕ����������� | |||||
| �P�j�@�����@ | |||||
| �@���ێ���Ɋւ��_�̓����Ƃ��āA�����@�iGoverning law�j�ƕ������������iDispute Resolution�j���d�v�ɂȂ�܂��B�����ł��������@�Ƃ́A�_������̉��߂̊�Ƃ��Ăǂ��̍��̖@����K�p���邩�Ƃ������ł��B��������̏ꍇ�A�����@�͓��R�A���{�@�Ȃ̂ŏ����@�̋K�莩�̂����݂��Ȃ��̂��قƂ�ǂł��B���{��Ƃƃ^�C��ƊԂ̔̔��_��ɂ��A���{�@��K�p�����A�Ƃ������߂ɂȂ邪�A�^�C�@��K�p�����B�Ƃ������߂ɂȂ�Ƃ������Ƃ����肤��킯�ł��B���{��Ƃ��炷��A�^�C�@�̓��e�̓��[�J���ٌ̕�m�Ɋm�F���Ȃ����蕪����Ȃ��킯�ł�����A���R�A�����@�͓��{�@���L���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B | |||||
| �Q�j�@������������ | |||||
| �@��������ł��A�Ⴆ�u�{�_��Ɋ֘A���镴���ɂ��Ă͑��n���ٔ�����ꑮ�I���ӊNJ��ٔ����Ƃ���B�v�Ƃ��������ӊNJ�������t���邱�Ƃ�����܂��B����ɑ��āA���ێ���̏ꍇ�́A���������ٔ����ɂ��ٔ��Ƃ��������������@�ŗǂ��̂��A���邢�͍��ے��ً@�ւɂ�钇�فiArbitration�j���ǂ��̂��Ƃ����Ƃ��납��l���A����ɂ��̏ꏊ���ǂ��ɂ���̂��Ƃ������Ƃ��l���邱�ƂɂȂ�܂��B �@���́A���ێ���̏ꍇ�ɒ��قɂ���P�[�X�������̂��ƌ����A�Ⴆ�A�^�C��Ƒ���̌_�ő��n���ٔ�����ꑮ�I���ӊNJ��ٔ����Ɏw�肵���Ƃ��āA���ۂɕ����������đ��n���ٔ����ōٔ��������Ƃ��܂��B�����œ��{��Ƃ����i�������Ƃ��Ă��A�����ɂ̓^�C��Ƃ̃^�C�����ɑ��݂�����Y�ɂ͋������s���ł��Ȃ��Ƃ�����肪���邩��ł��B���Ȃ킿�A���{�̍ٔ����̔����̌��͂́A��{�I�ɓ��{�����ł̂ݗL���ł���A�K�������O���ł��̗L�������F�߂��ċ������s�ł���Ƃ����ۏ͂Ȃ��A�ň��̏ꍇ�A������x�A�O���ōٔ�����蒼���K�v�������Ă��܂��킯�ł��B �@����A���ے��ً@�ւɂ����钇�قł���A���ُ��i�j���[���[�N���j�ɉ������Ă��鍑�X�ł͗L���ɂ��̔��f�����͂�L���A�������s���\�ł���A�����̍������_��ɉ������Ă��邱�Ƃ���A���ێ���ł͍��ے��ً@�ւɂ�钇�ق��������@�Ƃ��đI�����邱�Ƃ���ʓI�ɂȂ��Ă���킯�ł��B �i�������������̋�̗�j �@All disputes, controversies or differences which may arise between the parties hereto, out of or in relation to or in connection with this Agreement shall be finally settled by arbitration in Osaka, in accordance with the Commercial Arbitration Rules of The Japan Commercial Arbitration Association. �@��L�ł́A���ْn����ɂ��Ă��܂����A�������Ƃ����{�ł̒��ق�������ꍇ�ɁA��O���i���`��V���K�|�[���j�𒇍ْn�Ƃ��č��ӂ��邱�Ƃ�����܂��B�A���A���̏ꍇ�A����������������A���[�J���ٌ̕�m��T�����ƂɂȂ�A�J�͂ƃR�X�g���������邱�Ƃ͊o�債�Ȃ���Ȃ�܂���B |
|||||
| �U�D�܂Ƃ� | |||||
| �@����Ȃ��p���ł����Ɍ���������������Ƃ������ƂŁA�悭���e�����������ɒ��Ă��܂��Ƃ����̂������Ƃ��댯�ȑΉ��ł��B���ɍ��ێ���ɍۂ��ẮA���ӂ��������b�����ʼn�������Ƃ��������{�I�����͑S���ʗp���Ȃ����Ƃ��炷��A��������̌_��ȏ�ɂ��̓��e�ɂ͒��ӂ���K�v������܂��B | |||||
| �ȏ� |
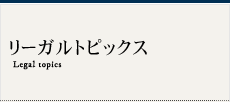
- �@�@�@�@