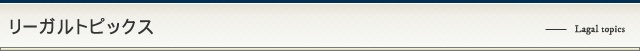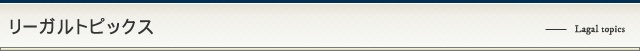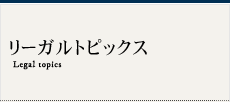ホーム > リーガルトピックス >令和6年>「財産を全てまかせる」旨の遺言について、包括遺贈する趣旨の遺言であると解された事例
「財産を全てまかせる」旨の遺言について、包括遺贈する趣旨の遺言であると解された事例
(大阪高裁判決 平25.9.5 判時2204号 P39~)
弁護士 松本史郎
令和6年12月2日更新
| 1 事案の概要 |
| (1) |
訴外Aは、平成20年2月14日死亡しましたが、平成17年11月11日、「私が亡くなったら財産については私の世話をしてくれた長女のXに全てまかせますよろしくお願いします」との自筆証書遺言(以下「本件遺言」といいます)をしました。
Ⅹは、本件遺言によって、AがY(銀行)に対して有していた普通預金及び定期預金(以下「本件各預金」といいまう)を遺贈されたと主張し、Yに対して1010万円余の支払を求めました。
|
| (2) |
一審の大阪地方裁判所堺支部判決(平25・3・22)は、本件遺言は、Aの預貯金の払い戻し等の手続を行い、財産の所在を最も良く把握しているXに対し、遺産分割手続を中心となって行うよう委ねる趣旨であると解するのが相当であると判断し、Xの本件遺言による遺贈に基づく本訴請求を棄却しました。 |
| (3) |
そこで、Xは控訴しました。本判決は、後記2記載の事実認定及び判断のとおり、本件遺言書作成当時の事情及び亡Aの置かれていた状況に鑑みると、本件遺言は、亡Aの遺産全部をXに包括遺贈する趣旨のものであると理解するのが相当であると判断して、Xの本訴請求を認容しました。
|
| 2 事実認定及び判断 |
| (1) |
亡Aは、平成15年2月から、妻Bと共に、大阪府河内長野市内に所在するbケアハウスに入居し、本件遺言をした平成17年11月11日当時もbケアハウスに入居していたが、bケアハウスに入居中の亡A夫婦のもとをしばしば訪れて、その世話をしていたのは専ら大阪府河内長野市内に居住する控訴人Ⅹ(以下、単に「Ⅹ」といいます)である。他方、Ⅹの妹夫婦は、亡A夫婦との関係が円滑さを欠くようになったため、生駒の自宅を出て、亡A夫婦と別居した後は、亡A夫婦と疎遠な関係になり、本件遺言がされた当時は、ほとんど交流が途絶えていた。また、Ⅹの別の妹も、遠方に居住している関係で、年2、3回程度しか亡A夫婦のもとを訪れることができなかった。そのような事情があったため、本件遺言をした当時、亡A夫婦の世話や亡A死亡後のBの世話を頼めるのはⅩしかおらず、亡Aは、Ⅹを信頼し、頼りにしていた。このことは、亡Aが、平成16年9月6日に、郵便貯金の解約等の手続をⅩに委任したり、本件遺言をした後である平成18年7月12日に、Ⅹに対し、700万円を贈与したりしていることからも窺い知ることができる。 |
| (2) |
このような本件遺言書作成当時の事情及び亡Aの置かれていた状況にかんがみると、「私が亡くなったら財産については私の世話をしてくれた長女のXに全てまかせますよろしくお願いします」という本件遺言は、被控訴人らが主張するような遺産分割手続を委せるという意味であるとは考え難く(本件遺言が遺産分割手続をすることをⅩに委せる趣旨であるとすると、そもそもそのような遺言は無意味である)、亡Aの遺産全部をⅩに包括遺贈する趣旨のものである、と理解するのが相当である。 |
| (3) |
なお、被控訴人らは、亡Aが平成14年6月11日付遺言及び平成14年10月15日付遺言では「相続させる」という文言を使用していたものであって、「まかせる」との表記は遺贈を意味しない、と主張する。
しかし、平成14年6月11日付遺言は弁護士の関与の下に公証人が作成した公正証書によってされたものであり、また平成14年10月15日付遺言も、一定の法律知識を有する者が関与してされたものであること、本件遺言書は、93歳で体調も決して良いといえなかった亡Aが自ら作成したものであることからすると、平成14年6月11日付遺言と平成14年10月15日付遺言の各遺言書に「相続させる」という表現が使用されていることをもって、亡Aが「相続させる」との表現と「全てまかせます」との表現との法律的意味の違いを認識し、本件遺言においては、「相続させる」と区別して「全てまかせます」という表現をした、と推認することができるとは到底いえず、亡Aが、包括遺贈の趣旨で「全てまかせます」と表記して、本件遺言をした、とみても何ら不合理であるとはいえない。したがって、被控訴人らの主張は採用できない。
|
| (4) |
そうすると、亡Aは、本件遺言によって、本件各預金を含む亡Aの遺産全部をⅩに対して包括遺贈したといえるから、Ⅹは、本件各預金全部を取得したことになる。
|
| 3 コメント |
| (1) |
遺言は、自筆証書によってすることができます。右証書については瑕疵があるものが少なくないため、その方式、遺言の内容等に関し争われることが多いです。 |
| (2) |
遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書全記載との関連、遺言書作成当時の事情などを考慮して遺言者の真意を探究し、遺言書の条項の趣旨を確定すべきである、とされています(最二判昭58・3・18裁判集民事138・277)。
自筆証書遺言では、右のような基準に従って真意を確定しなければならない事案が少なくないようです。
|
| (3) |
遺言の解釈の争いを避けるためには、公証人が作成する公正証書遺言の作成をお勧めします。 |
|
| 以上 |
|
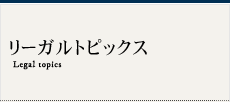
-